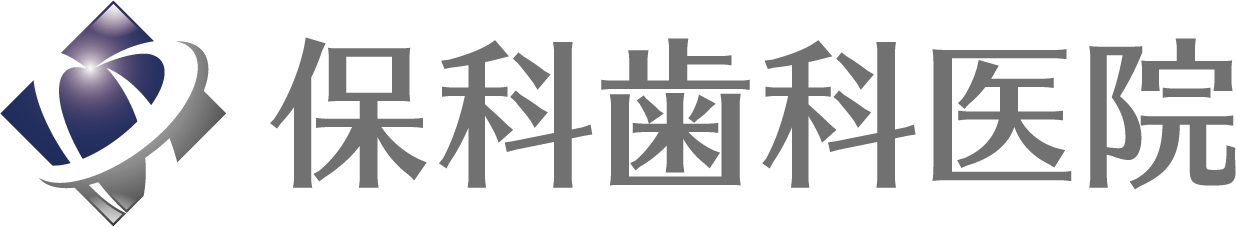生活歯の治療⑦
- 2025年2月10日
- 虫歯と歯周病
こんにちは!
保科歯科医院高輪の保科です。
2月も中旬に入りました。受験シーズンも後半戦だと思います。私立歯学部の一般入試は前期試験が1月下旬から2月上旬に行われます。正確には分かりませんが理学部や文学部もこの時期だと思います。すでに合格通知を手にした受験生も多くいるのではないかと思います。後期試験で受験される方や国立志望の方はもう少しだけ受験勉強が続きますが全力で頑張ってください。くれぐれもオーバーワークはしないでくださいね。本番前に体調を崩してしまうと元も子もないですから。
さて本日のブログは生活歯の治療の7回目です。今日は生活歯での治療に入る前に行う診査診断について解説したいと思います。前回のブログで保科歯科医院高輪での生活歯治療のボーダーラインはC3とある説明しました。C2では100%生活歯での治療を行い、C3は生活歯か失活歯かの見極めが重要になります。この見極めがいい加減だとその先の治療もいい加減になってしまうのです。繰り返しになりますが保科歯科医院高輪では生活歯は生活歯のまま治療を行います。言い換えると生活歯の神経を除去する治療である抜髄をして失活歯にする治療は行いません。失活歯はデメリットが多いからです。以前のブログに生活歯のメリットについて書いていますので、忘れた人は読み直してみてください。では生活歯の見極めはどのようにして行うのか。保科歯科医院高輪では下記の項目の通りとなります。
1.画像診断(X-Ray診断)
2.歯髄電気診
3.冷温熱反応試験
4.切削診
画像診断はおそらくどの歯科医院でも行っていると思います。Ⅹ-Ray撮影を行い画像として虫歯の範囲深度を診断します。記録として残りますし目視では見えない歯髄との距離を判定できます。画像として虫歯が見えるとういうことはすごく大切なことです。しかし画像では神経が生きているの死んでいるのかの判定はできません。根管治療済みで根管内に充塞材が入っていればわかりますが、未根管治療の歯では判定はできないのです。予想はできますけどね。そこで2~4の診査が必要となるのです。2.歯髄電気診は歯面に微弱な電気を流します。最初は極微量の電流ですが徐々に電流量を上げていきます。神経が生きている歯ではある程度電流が上がると痛みの刺激として電流を感じます。感じた瞬間に電気診を止めます。痛み刺激として電流を感じることができた歯は生活歯です。逆に何も感じない場合は失活歯である可能性が高いです。歯髄電気診の正確度は70~80%と言われています。20~30%は誤診してしまうということです。この誤診をなくすために追加の診査をします。それが3.冷温熱試験です。保科歯科医院高輪では歯科用の冷エアゾールで冷やしたスポンジ片を患歯に接触させて冷刺激として感じるか否かの試験をします。感じれば生活歯、感じなければ失活歯と判断します。冷反応試験の正確度は85%以上と言われています。電気診と併せてダブルチェックで歯髄の診査を行います。ほとんどの場合はこの2つの診査で判断がつきますが、まれに電気診では刺激を感じるが冷反応試験では無反応という矛盾した結果が出るときがあります。そのような場合は日を改めて再診査を行います。その日の患者さんのコンディションや精神状態、鎮痛剤服用の有無などで診断が曖昧になることがあるからです。それでも判断がつかないときには4.切削診を行います。切削診とは無麻酔で虫歯をそっと削っていき神経に近いところまで虫歯を削った刺激を痛みとして感じるか否かを確認します。神経が生きていれば通常は神経に近いところまで削ると痛みを感じるはずなのですが神経が死んでいる場合にはどこまで削ってっも痛みを感じないのです。切削刺激の反応を見極め生活歯か否かを判断すます。保科歯科医院高輪ではこの4つの方法で複合的に生活歯なのか失活歯なのかを判断してから治療に入ります。
ではまた!
〒108-0074東京都港区高輪3-7-8西町ビル3階A
℡03-5422-7322
保科歯科医院HoshinaDentalClinic【港区/高輪/白金/品川】